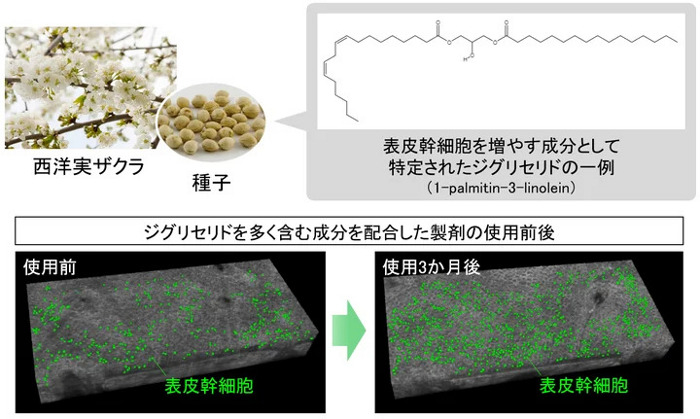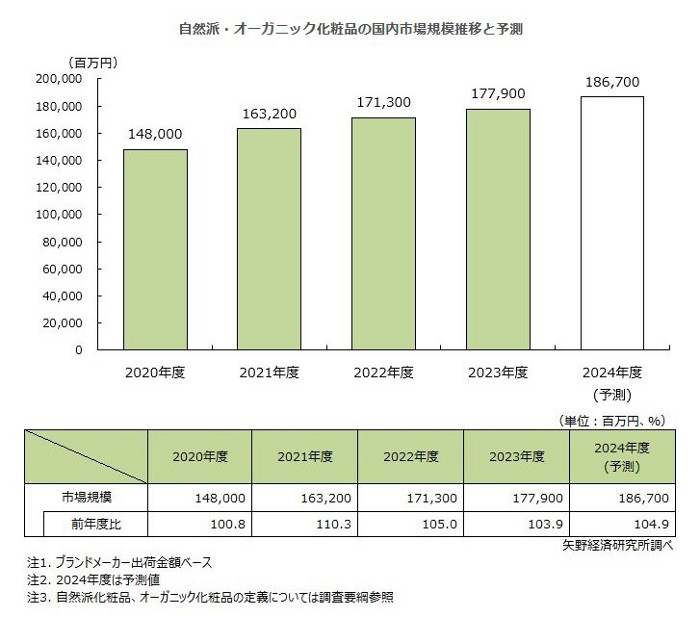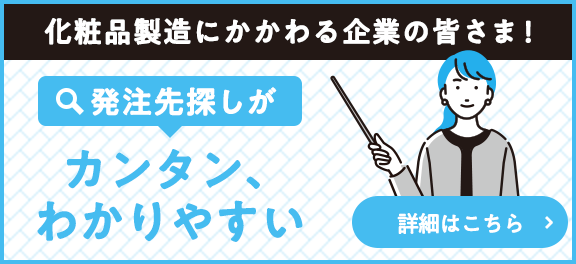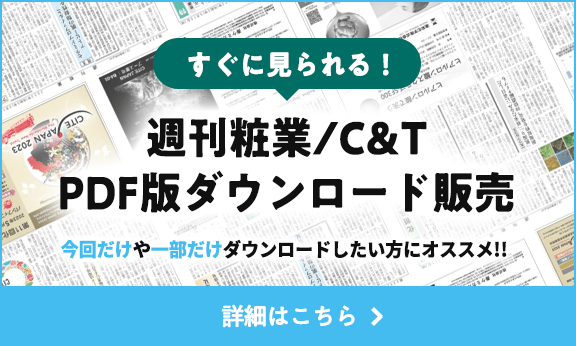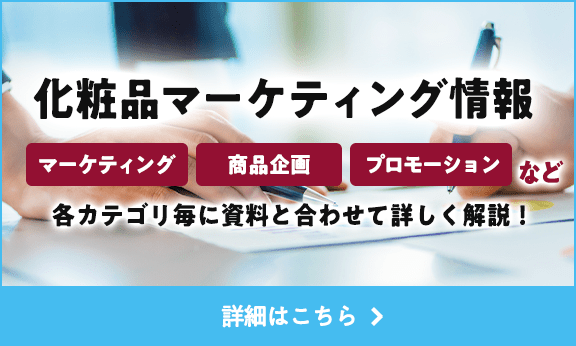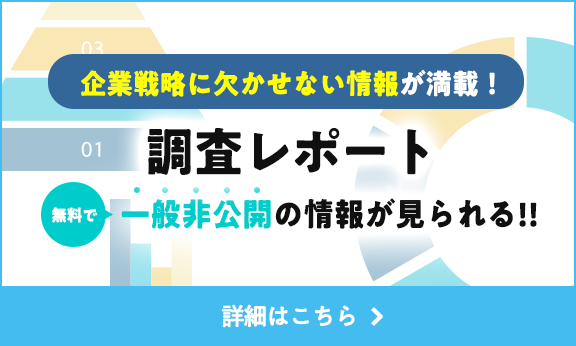ヒノキ新薬 阿部武彦社長、デジタル化の目的は販売店と顧客をつなぐこと
カンタンに言うと
- ――化粧品業界で進む「デジタル化」について、率直な意見や感想をお聞かせください。
- ――化粧品業界でデジタル化を進めていくべき点と、貴社の現在進めている取り組みについてお聞かせください。
- ――貴社では現在、デジタル活用でどのような取り組みを行っていますか。


この記事は週刊粧業 2022年1月1日号 41ページ 掲載
■2022化粧品日用品主要業態の最新トレンド(百貨店)~顧客を軸にした施策が重要に■2021年化粧品関連新製品発売動向、男性化粧品の販売数が大幅増、コロナ禍に対応した商品が好調◎化粧品~ニューノーマル対応に軸足◎日用品~品目別(洗剤・洗浄剤・仕上げ剤、口腔衛生品、消臭・脱臭・芳香剤、衛生・救急製品、紙製品、シェービング、その他日用品類)発売状況■特集/アフターコロナを見据えた攻めのOMO戦略...
PDF記事・人気ランキング

バラ売り
400円
【週刊粧業】2024年下期オーラルケアの最新動向

バラ売り
400円
【週刊粧業】2024年パーソナライズドコスメの最新動向

バラ売り
400円
【週刊粧業】2024年ヘアケアの最新動向

バラ売り
300円
【週刊粧業】2024年アジアンコスメの最新動向
最新PDF記事

バラ売り
300円
【週刊粧業】2024年アジアンコスメの最新動向

バラ売り
200円
【週刊粧業】ビズジーン、遺伝子検査技術を様々な分野に活かす

バラ売り
200円
【週刊粧業】Zenken、人材獲得と企業ブランディングを両立したサービスが好調

バラ売り
200円
【週刊粧業】2024年・年末大掃除の最新動向
人気記事ランキング
インタビュー
人気記事ランキング
ライブラリ・無料
ダウンロードコーナー

PDF版 ダウンロード販売
気になる刊行物をPDFで
ダウンロード
紙面を探す

化粧品
マーケティング情報
マーケティングに役立つ
情報が満載
紙面を探す

調査レポート
化粧品業界での戦略に
役立つレポート
レポートを探す

粧界データ集
メーカー製品一覧などの
データ集をダウンロード
無料でダウンロード

化粧品容器カタログ
ライブラリー
容器メーカーの
最新カタログを公開中
カタログを探す

デジタル紙面版
2010年1月から最新号まで
デジタルアーカイブ化
無料で見る
刊行物紹介

週刊/毎週月曜日発行
週刊粧業
化粧品、日用品、医薬品、美容業、装粧品、エステティック等を中心とした生産・流通産業界の総合専門情報紙。

季刊/年4回
C&T
化粧品、日用品、アクセサリーなどの業界別の市場動向をはじめ、戦略、流通、経営、マーケティングを扱う情報専門誌。
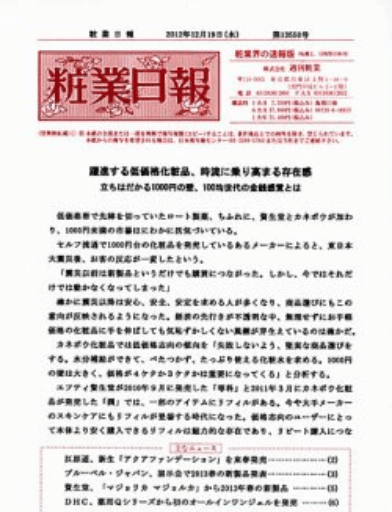
週刊/毎週月曜日発行
粧業日報
化粧品、トイレタリー、石鹸、歯磨、日用品に関する情報の速報版。業界のエグゼクティブ必読の情報紙。
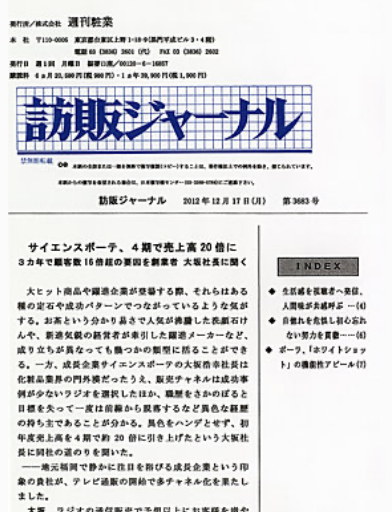
週刊/毎週月曜日発行
訪販ジャーナル
昭和33年に創刊された、わが国初の訪問販売化粧品業界の専門情報紙。
更新情報(PR)
速報ニュース
アクセスランキング
- 日間
- 週間
- 月間